【トレーニングガイドの取り扱いのお願い】
※トレーニングガイドをホームページなどに転載や引用する場合は、必ず事前に許可を取り、かつ出典を明記してください。
許可願い連絡先:関西医科大学看護学部 三木明子

暴力への対応トレーニングガイド
本トレーニングガイドは、在宅医療・ケアの従事者に対する利用者や家族からの暴力(ハ ラスメントを含む)行為を防止するために必要な事業所の予防策やトレーニングについて 明示することで、経営者、管理者、従業員が安全かつ的確に対応することを目的として、 作成したものです。暴力防止プログラムは、(1)経営者の積極的取り組みと従業員の参加、(2)職場分析、(3)危険の防止と管理、(4)暴力防止トレーニング、(5)記録とプログラムの評価 で構成されています。トレーニングのテーマを決める際にも、各事業所の状況に応じて、ガイドの内容をヒントにご検討ください。各自で点検する「暴力防止プログラム・チェッ クリスト」、評価者が点検する「暴力防止プログラムの評価チェックリスト」も活用くだ さい。
ダウンロードボタンでPDFが開きます
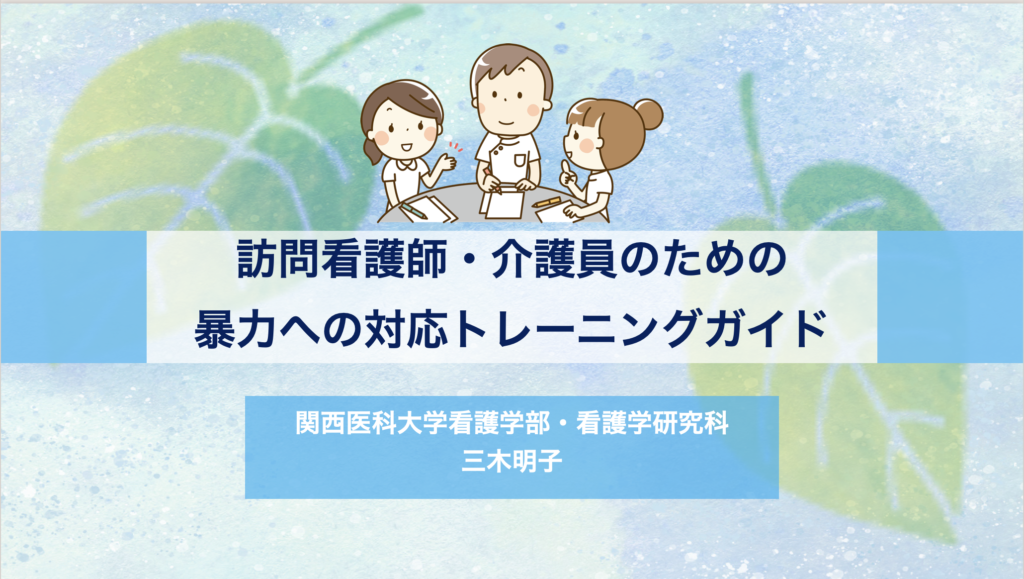
暴力への対応トレーニング動画(You Tube)
暴力への対応トレーニング動画は、在宅医療・ケアの従事者が職場暴力対策について、学習するための教材として作成しました。各事業所が適切な対応がとれるよう、研修や個人学習に活用ください。ただし、個人学習だけの利用は推奨しておりません。この機会に、事業所で研修を実施し、事業所における暴力対応について、全員で話し合って決めていくことが重要です。なお、研修の際には、暴力への対応トレーニングガイドをダウンロードしてお手元にご準備ください。
視聴するで動画がご覧いただけます